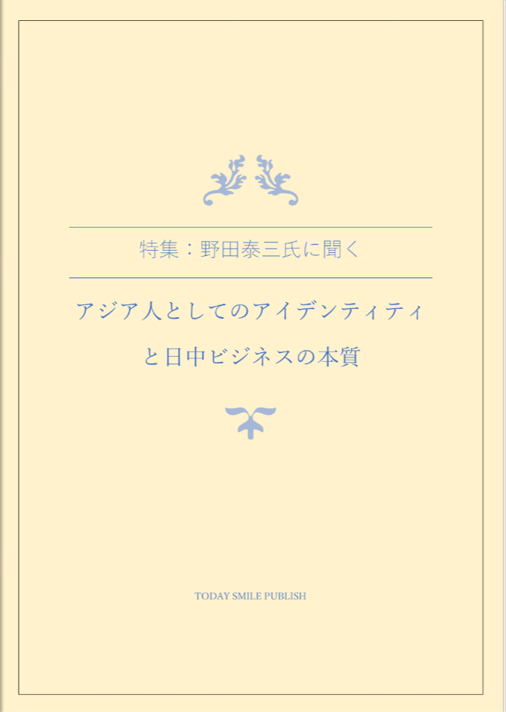
野田泰三氏は、創業100年を超える株式会社セラリカ野田の社長です。https://ceraricanoda.com/company/history 1990年代にアジア関連のビジネスを経験しました。その生の体験とそれに基づくユニックな御考えを語っています。
イントロダクション:
長年にわたり、日中ビジネスの最前線で活躍されてきた野田社長泰蔵氏。今回は、野田社長氏が過去の経験から得た深い洞察と、アジア人としての独自の視点に焦点を当て、お話を伺いました。90年代の中国での体験、日本人と中国人の国民性の違い、そしてビジネスにおける本音のコミュニケーションの重要性まで、多岐にわたるテーマについて語っていただきます。
程教授: 本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。早速ですが、先日のお話の中で「アジア人野田泰三」という言葉が非常に印象的でした。この言葉に込められた思いについて、改めてお聞かせいただけますでしょうか。
野田泰三社長(以下、野田社長氏社長): ええ、ありがとうございます。90年代に中国に頻繁に行き、北京で多くの方々と交流する中で、私自身が「アジア人」として受け入れられていると感じる瞬間が何度かありました。特に印象的だったのは、中国の方々が親しみを込めて「イエテェンタイサン」と呼んでくれたことです。
程教授: 「イエテェンタイサン」ですか、面白いですね。
野田社長: はい。日本語の「野田泰三」を中国語風に発音したものだと思いますが、その呼び方に、日本人というよりもアジアの仲間として受け入れられているような温かさを感じました。毎日のように夜遅くまで、本当に多くの中国の方々と食事を共にし、様々な議論を交わしました。
程教授: 日本人同士だと、そこまで中国の方々と深く交流することは珍しいかもしれませんね。
野田社長: そうですね。多くの日本人は、中国にいても日本人同士で集まる傾向があるように感じました。しかし、私は幸運なことに、通訳として京都大学で博士号を取得した優秀な人物が常にそばにいてくれ、言葉の壁を感じることなく、中国の方々と本音で語り合うことができました。
程教授: 夜の交流では、どのような話題が多かったのでしょうか?
野田社長: 90年代は中国が大きく変化していく時期で、北京の方々は、私に新しい考え方を求めていたように思います。科学技術新聞の幹部の方々をはじめ、様々な分野の方々と議論を交わしました。資本主義の経験を持つ私に対して、彼らは多くの質問を投げかけてきました。
程教授: 具体的にはどのような分野の方々と?
野田社長: 文化人、大学教授はもちろん、北京体育大学の幹部や林業科学院の研究者など、多岐にわたります。特に林業科学院の方々とは、環境問題や貧困問題など、中国が抱える課題について深く議論しました。
程教授: 学会では環境部会の座長に指名されたそうですね。
野田社長: はい、林業科学院の国際シンポジウムで、学位もない私を座長に指名していただきました。日本人であるにもかかわらず、です。シンポジウム後には、欧米系の参加者がいなくなった後で、中国の方々との間で本音の議論が始まりました。そこで、改めて自分がアジア人として受け入れられていると感じました。
程教授: まさに本音のコミュニケーションですね。どのようにして、そのような深い関係性を築かれたのでしょうか?
野田社長: 大手商社が政府高官と会談する際には、綿密なシナリオを用意すると聞きますが、私はそうではありませんでした。90年代の林業大臣との面談やパーティーで感じたのは、大臣が本質的なこと以外には興味がない、ということでした。
程教授: 本質的なこと、ですか。
野田社長: ええ。日本の企業側は、いかに大きな案件をまとめるかに意識が集中していましたが、大臣はもっと長期的な視点、文化的な交流に関心を持っていました。例えば、日本の和服の帯について、その歴史や文化的な背景を深く理解しようとしていました。
程教授: ビジネスの視点と文化的な視点、そこにギャップがあったのですね。
野田社長: そうです。日本の企業はプロジェクトの成功ばかりを重視しがちですが、中国の政治リーダーたちは、もっと長い歴史観、文化交流の視点から物事を捉えている。そこに、日中の意思疎通の難しさがあると感じました。今後は、歴史や文化に対する理解を深め、長期的な視点での交流を目指すべきだと痛感しました。
程教授: まさに感性の違い、違和感から理解が生まれるのですね。
野田社長: そう思います。相手との違いを認識し、尊重することから、本音のコミュニケーションが始まり、共通の課題解決へと繋がっていくのではないでしょうか。利他的な発想、つまり「相手と一緒に良くなる」という考え方が非常に重要だと考えています。
程教授: 先生との出会いも、そのような考え方が基盤にあったのですね。
野田社長: はい、カワカツ先生との出会いも、共通の課題に対する関心から始まりました。互いに良い方向へ進む道を模索するという、利他的な発想が、信頼関係を築く上で不可欠だと考えています。
程教授: 90年代の中国の幹部の方々と交流する中で、日本の強み、中国の強み、またそれぞれの課題を感じられたことはありますか?
野田社長: 話が合う人と合わない人がいるのは当然ですが、特に文化大革命を経験された世代の方々との間には、大きな隔たりを感じました。イデオロギーを振りかざし、口先ばかりで行動が伴わない。一方、体育大学の幹部の方々のように、体を使い、実践を通して真理を追求する人々とは、非常に深いレベルで共感し合えました。
程教授: イデオロギーと行動、そこがポイントなのですね。
野田社長: ええ。イデオロギー偏重ではなく、行動を通して示すことの重要性を感じました。特に中国の伝統的な文化、例えば太極拳や気功には、西洋的な激しさとは異なる、アジア的な新しい発想があるように思います。北京体育大学の幹部の方々が、気功や太極拳、超能力といった分野に関心を持ち、研究していることにも、その現れではないでしょうか。
程教授: 日本人の国民性についてはいかがでしょうか?
野田社長: 90年代の日本は、若者の勢いが失われつつある時期でした。80年代までの高度成長期とは異なり、閉塞感が漂っていました。国費留学生として日本に来ていた中国の若者たちと比べると、日本の若者は生活力、つまり生きる力に欠けているように感じました。
程教授: 生きる力、ですか。
野田社長: はい。当時の日本の若者は、生活のために稼ぐという感覚が薄れ、大学や大学院に進学することが当たり前になっていました。しかし、学ぶことへの意欲、ハングリー精神は、中国の留学生の方が圧倒的に強かった。彼らは、一旗揚げよう、成功しようという強い意志を持っていました。
程教授: 豊かさを達成した後の日本の課題が見えてきたのですね。
野田社長: そうですね。豊かさを達成し、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」になった後、若者がどのように変化していくのか。バブル経済とその崩壊を経て、90年代の日本は停滞期に入りました。当時、日本の企業よりも、中国の企業のほうが成長していくのではないかと感じたこともありました。
程教授: 生きる力や勢いの違いは、具体的にどのような点に現れていたのでしょうか?
野田社長: 日本の若者は、生活が保障されている中で育ち、ハングリー精神が薄れていったように思います。一方、中国の留学生は、経済的に恵まれない環境から抜け出し、成功を掴もうという強い意志を持っていました。その差は、学ぶ姿勢、貪欲さ、そして何よりも生きる力として現れていたように思います。
程教授: 中国と日本の差を冷静に見つめる必要がある、と。
野田社長: ええ。日本の教育、特に高等教育において、知識偏重の傾向が強まり、倫理観や他者への配慮といった側面が軽視されているのではないかと感じます。中国の留学生の中には、日本人学生の生活力の弱さを見下すような態度も見られ、それが日中間の壁になっているようにも感じました。
程教授: 価値観の違い、世代間のギャップ、様々な要素が複雑に絡み合っているのですね。
野田社長: そうですね。現代の中国も変化していますが、90年代の経験は、日中関係の本質、そしてアジア人としてのアイデンティティを考える上で、非常に貴重な示唆を与えてくれます。
——–
程教授: AIの言語処理能力は目覚ましい進歩を遂げていますが、言葉の壁を越えても、文化や感情の壁は残りますよね。AIは、言葉だけでなく、その背景にある文化や感情、言葉にできない本音まで理解できるようになるのでしょうか?
野田社長: おっしゃる通り、言語は文化や感情と深く結びついています。AIが言葉を翻訳できても、その言葉が持つ文化的ニュアンスや感情的な重み、あるいは言葉にされていない行間を読むことは、まだ難しいかもしれません。
程教授: 特に異なる文化圏の人々の間では、言葉以上に文化的な背景や価値観の違いがコミュニケーションの障壁になることがありますよね。
野田社長: ええ、まさに言語の問題だけではないのです。文化、歴史、価値観、そういった目に見えない要素が、コミュニケーションの質を大きく左右します。しかし、AIの進化は、そうした課題を克服する可能性を秘めていると私は考えています。
程教授: AIの可能性、ですか?
野田社長: はい。AIはシンギュラリティという概念と結びつけて語られることが多いですが、私は技術には常に裏と表があると思っています。原子力が良い例でしょう。平和利用も可能ですが、広島や長崎の悲劇を生んだ兵器にもなり得ます。AIも同様に、使い方次第で人を生かすことも殺すこともできる、両刃の剣なのです。
程教授: 技術の二面性、それはAIにも当てはまるのですね。
野田社長: ええ。私は昆虫の研究を通じて、「殺す発想」と「生かす発想」の対比を常に意識してきました。農業は典型的な昆虫を「殺す」産業ですが、JICAプロジェクトなどを通じて、「虫を生かす」発想での産業の可能性も追求してきました。AIも、人間の創造性を奪い、仕事を奪う「殺す」技術にもなり得ますが、人々の生活を豊かにし、新たな価値を生み出す「生かす」技術にもなり得ます。
程教授: 「業績の向上と人間性の向上」の両立、AIにもその視点が必要だと。
野田社長: その通りです。業績向上は技術のパワーですが、そのベクトルを定めるのは人間性です。AI技術も、人間性の向上、つまりみんなが幸せになるためにどう活用できるかを常に考えるべきです。李先生とのプロジェクトも、その理念に基づいて進めています。先端技術を中国の貧しい農民を豊かにするために役立てる。それが根本的な目的です。
程教授: 技術発展と人間性の向上、両輪で進むことが重要だと。
野田社長: ええ。そして、言葉と文化の関係に話を戻すと、AIは言葉の歴史、文化の歴史を深く理解する上で大きな力になると考えています。ワープロの登場が日本語の文化を救ったように、AIもまた、言葉の文化を豊かにする可能性を秘めているのです。
程教授: ワープロが日本語文化を救った、というのは興味深い視点ですね。
野田社長: 日本語は漢字文化であり、その複雑さゆえに何度も滅亡の危機に瀕してきました。しかし、1970年代にワープロが登場し、漢字を容易に扱えるようになったことで、日本語は再び活力を取り戻しました。AIも同様に、言語の壁を乗り越え、多様な言語や方言、文化を包含し、言葉の持つ豊かな歴史と文化を未来へと繋いでいくことができると期待しています。
程教授: AIが多様な文化と言葉を包含し、文化発展を促進する、壮大なビジョンですね。
野田社長: ええ、AIは多様性(ダイバーシティ)を受け入れ、それぞれの良さを活かすことを可能にします。アメリカのショービジネスが多様性を力に変えて発展したように、AIもまた、多様な文化を融合させ、新たな価値を創造する力を持つでしょう。東アジア、そしてアジア全体が、そのような役割を担うべき時に来ており、AIはその強力な推進力になると信じています。
程教授: AIによってアジアが団結し、文化で世界をリードする時代が来るかもしれませんね。
野田社長: パワーで押し通す時代は終わり、文化で惹きつける時代が来ると私は見ています。その中心となる技術がAIでしょう。AIは人間のデータ、思考を学習し、成長していく過程で、パワー的な文化と利他的な文化、両方を吸収するでしょう。どちらの文化をより強く反映するか、どのような価値観に基づいて判断するようになるかは、今後のAIの進化次第です。
程教授: AIの価値観形成、倫理観が重要になってきますね。
野田社長: ええ。AIがニヒリズムに陥らず、人間性を尊重し、利他的な方向へ進むことを期待しています。アメリカの知識人の中には、ニヒリズムに陥り、社会を混乱させている人々もいますが、AIにはそうならないでほしい。ニヒリズムではなく、人類全体を幸福にする方向にAIが発展していくことを願っています。
程教授: ニヒリズムは深いテーマですね。AIが哲学的なゾンビになる可能性も議論されています。まるで人間のように言葉を理解し、答えるAIが、本当に心や魂を持つのか、持たないのか。
野田社長: AIの倫理的な問題、哲学的な問題は、まさにこれから深く議論していくべき重要な課題です。AI技術は急速に進歩していますが、その進むべき道、人類社会にとって望ましい未来のあり方を、私たち人間自身がしっかりと見定め、AIを導いていく必要があります。
程教授: 未来のAI、そして人間の未来。壮大なテーマですね。少し時代を遡って、90年代の中国でのプロジェクトについてお伺いしてもよろしいでしょうか?どのようなきっかけで、中国に滞在され、具体的にどのようなプロジェクトに関わられたのでしょうか?
野田社長: 90年代に中国に頻繁に行くようになったきっかけは、JICA(国際協力機構)のプロジェクトでした。林業分野での協力プロジェクトで、私は専門家として派遣されました。約1000日間、北京を中心に滞在し、中国の林業科学院や北京体育大学など、様々な機関と協力して研究や人材育成に取り組みました。
程教授: 90年代、そして現在、そして未来。時間軸で見た変化や展望について、お聞かせいただけますでしょうか?過去、現在、未来への主観的な期待でも結構です。
野田社長: 90年代は、中国が改革開放政策を推進し、急速な経済成長を遂げている時期でした。人々の活気、エネルギーに満ち溢れていました。日本はバブル崩壊後で、閉塞感が漂っていた時期でした。現在、中国は経済成長のスピードは鈍化していますが、技術力、特にAI分野では世界をリードする存在になっています。日本は、技術力は高いものの、社会全体に閉塞感が依然として残っているように感じます。
程教授: 未来への展望はいかがでしょうか?
野田社長: AI技術が、日本を含むアジア全体の文化、経済、社会を大きく変革する可能性を秘めていると信じています。AIを人間性、倫理観に基づいて発展させることができれば、アジアは再び世界の中心となり、文化と技術の両面で世界をリードする存在になれると確信しています。
程教授: 本日は、非常に興味深いお話をありがとうございました。
野田社長: こちらこそ、ありがとうございました。株式会社セラリカNODA野田 剛弘


